連載
「宇多喜代子の本棚」[4]
2020.8.1
富永始郎の句集『
眞木
』 |
 |
多くの俳人を擁する俳壇という大きな場も、腑分けをしてゆけば各地の小規模の句会の集積である。句会に関しては、たとえば多くの人口や情報を擁する都市が中央で、遠く離れた山間僻地が地方だという物言いは通用しない。中央とは、自らが居るところ、個が軸を立てたところ、めいめいの作品の磁場、そこだと思えばいい。
私にとってしっかりと自らを中央におき、存分に俳句人生を生きた見本のような一人が寺田京子であった。先年、その句業をまとめた『寺田京子全句集』(現代俳句協会刊)が刊行され、北海道を中央として俳句を続けた寺田京子の句が多くの方々の手に届いた。
いま一人に、たまたま寺田京子と同じく加藤楸邨の「寒雷」の俳人であった沖田佐久子がいる。沖田佐久子は第二回(1956)角川俳句賞の受賞者であり、初学時代の私も、たどたどしく受賞作「冬の虹」を読んだ。おぼつかない読み手ではあったが、それでも当時の社会性俳句に適った句を残した女性はといえば、たぶん沖田佐久子だといえるのではないか、そんなことを思っていた。そのことを句会の席で話題にしたことがあり、同席の老仲間に「あんまり社会性というのにはまらんように」とたしなめられた。

その沖田佐久子と同郷の佐賀の俳人に富永始郎(富永寒四郎)がいる。同じく「寒雷」の作家で、「寒雷」「杉」を通して森澄雄の盟友でもあった。この富永始郎もまた佐賀を自らの中央として虚飾のない句を多く残した一人である。
たまたま佐賀在住の友人・斎藤純が沖田佐久子を慕いつづけていた縁で、幾度か佐賀に行き、斎藤純や松田美奈らと懇談し吟行に同道した思い出がある。寺井谷子を誘い出したのは小城(おぎ)町の清水の滝への吟行の時、
秋暑し鯉一匹をたいらげて 寺井谷子
を残してくれていて、当日のことを思い出すよすがになっている。富永始郎の俳句を知ったのも、佐賀の俳人たちとの縁による。

富永始郎には『眞木』という句集が残されている。これには昭和15年から同28年までの句を収録した『明日』の357句と、その後の『明日以後』の365句が収められている。いま読んでも胸をつかれるような多くの秀句を収した句集である。
あらためて全句通読して思うことは、俳句の一句一句は小さく見えるが、この一集は富永始郎という一人の人間の人生の実感を語った大きな人生録であるということだ。ある時は父親として、ある時は心もとない病者として、ある時は不朽の青年として、その時その時を真摯に生きてきた力の塊の結集だと思わせる句集である。
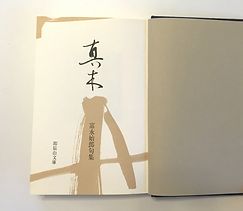
当節の若い方々には、寺田京子、沖田佐久子、富永始郎などが生きた時代の、戦時中、敗戦、敗戦後、療養俳句などの言葉の背景は分からないだろうが、これは当然のこと。そこを分かってもらうには、多少の解説や予備知識が必要となろう。だが、そんな解説などとは関係なく、人間として分かり合えるところがあれば十分である。
さて、「富永始郎」には、もう一つ「寒四郎」の名がある。敗戦直後、地元に寒十夜吟という勉強会があったとのこと、「寒雷」での名はその勉強会の会名に因む「寒四郎」である。その後、昭和45年に森澄雄が「杉」を創刊した際には、「始郎」の名で最初からこれに参加している。「寒雷」の後輩・齊藤美規によれば、遺句集となった『眞木』の出版に関しては、森澄雄が選句、集名、序文などの一切を面倒をみたとのこと(「麓」86号)。まさに盟友であったのだ。

残念なのは、富永始郎に関しての年譜の詳細が不明なこと、そのことを尋ねたい人がみな故人となり、たどる手立てがないということである。分かっているのは、生年が大正2年、没年が昭和61年12月であることのみ、今の私の手元にはそれ以外の俳句にかかわる動向を知る資料はない。生前、小城高校の教師の職についておられたこと、肺を侵され三養基郡(みやきぐん)中原の国立佐賀療養所に入所、ここで何年かの療養生活を過ごしていることなどが作品から推測できる。斎藤純さんに、もっと多くを聞いておくべきであった、そんな悔いが残るばかりである。
無花果の冬枝あかるし母と子に
大樟の葉降らすもとに吾子育つ
凩や子が泣く聲は我が泣く聲
わが黙に背の子ももだす遠雪嶺
懐に子の悴みのほぐれゆく
風邪汚れして子の面輪われに似ぬ
長女誕生以来、その子への愛情と、子との一体感を感じ取ることができる句である。手の込んだ技巧がなく、一読共感できる。
富永始郎は俳句を始めた若い時から旧態依然とした俳句に懐疑的で、昭和初期に活躍していた日野草城や西東三鬼らの句集を耽読し、水原秋櫻子、石田破郷、加藤楸邨らの俳句に啓発され俳句に入っている。富永始郎の生来の資質が、これらの俳人の句を心の糧とするのによく合ったのであろう。でありながら、地元の句会では「ホトトギス」や「同人」の俳人たちと膝を交え、研鑽の日を過ごしている。そんな日を重ねつつ、やがて自由な句作を発表していた加藤楸邨の「寒雷」へと繋がってゆく。「寒雷」創刊が昭和14年、富永始郎が俳句を始めたのが昭和15年であった。「寒雷」では、同じくここで詩才を伸ばしていた森澄雄との交流や相互啓発も大きな力となっていった。
その後、佐賀を磁場として同人誌「菱の花」「偏西風」などを出している。これがやがて「寒雷」の衛星誌へと発展してゆく。そんな時期に富永始郎は胸部疾患に侵される。この罹患の不幸は妻に及び、次に子に及ぶ。富永始郎は療養所に入り、妻子とばらばらになる。
鵙に啼きすてられ静臥またはじまる
冬没日屍とらへて燃えあがる
夜の菊に成形の肋崖をなす
世を捨てし病者ばかりの焚火燃ゆ
妻子恋ふ胃の腑へ生牡蠣呑み下す
霊安所へ電線二本吹雪をり
静臥の眺め馬恍惚と霜に糞(ま)る
冬雪よ熱高き日に母は来る
ただ横たわっているだけの身の不安、逢えぬ家族への思い、句集『明日』の療養期の句には生の苦渋と透徹の心境があふれている。その中に「三月三日妻三人の娘に雛飾ることもせず入所、以来月餘共に歩行を許されず互に見舞ふことさへ出来ざりし」の詞で、
妻よ今朝燕来しを見たるかや
がある。なんとも切ない。やがて、「パス服用危機脱す」として、
鶏の骨手摑み喰らふ蝶舞ひ来
の元気を回復させる。そんな時に三女町子が同病で療養所に入ってくるのだ。
芋の葉の親露子露ころがりぬ
死に近き子を抱き眠る落葉の音
やがて不幸の連鎖で「十二月五日町子つひに永眠す」の日を迎えることになる。
隙間風に折鶴ゆるる吾子死にゆく
湯婆のそばに襤褸のごとく死なしめき
白菊もて汝が今生の身を埋(つつ)む
柩打ちし石は石蕗の日向に戻し置く
吾子出でて冬陽かたむく不浄門
子の死を前に父は慟哭の十句を残している。ここにはその内より五句を抽いた。町子の生涯は短かったが、父の作品の中に一期の生の証を留めたのである。病臥の日々にあって子との別れは、句集『明日』の峰となっている。
のちに始郎は胸郭成形手術を受け社会復帰をして、句集『明日』を刊行する。昭和28年12月30日が発行日、書肆ユリイカからの出版。これに尽力したのも森澄雄であった。ともに貧しい敗戦後、俳句を絆として助け合った友情の句集であった。
合歓の花水に鍋釜沈まする
嫁ぐ子よ水に目うかべ田の蛙
太陽はつねに全円凍世界
庭の牡丹壺の牡丹と風かよふ
酒断つは命惜しむか秋の風
咳四つこぼして生を終りたる
これらは「明日以後」よりの句。富永始郎の生涯は肉親との別れや病魔に翻弄されたところがあったが、〈太陽はつねに全円凍世界〉には、太陽に人力では抗えぬように、命運にもそんな世界があるという諦観の境地が窺えるのだ。絶句となったのは、
咳四つこぼして生を終りたる
であった。咳をするのは生きている証。なんとなく生前の我に決着をつけた、そんな最期である。
富永始郎は佐賀を中央として、その生の日のほとんどを俳句とともに生き、佐賀俳壇のためによく尽力した生粋の俳人であった。
